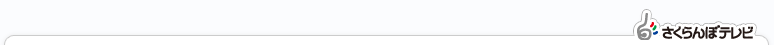
第二回「さくらんぼ文学新人賞」 選評
他の作者にはない美点
唯川恵
いつもながら、選考会は驚くほど意見がわかれる。小説というのは、読み手によってこれだけ印象が変わるという証だろう。全体としては、今回、少々バラエティに欠けていたように思う。ミステリーや時代小説、ホラーやファンタジーの応募もぜひ期待したい。また、タイトルにも一考を。
『愛の行為』は、生と死をテーマにしていて、その意欲は買いたいが、少々から回りしてしまったように感じた。加えて、私にはどうにも文体が馴染まなかった。主人公・道明も、僧侶という魅力的な職業にしたのだから、もう少し踏み込んで欲しかった。
『叙情的な癒し』は、主人公が落語家・春之助に惹かれる思いが伝わらず、物足りなさを感じた。劇団の実体は知らないが、そこまでひどい座長がいるものなのか。また、主人公の立ち位置が常に被害者で、読むには息苦しい。しかし、それが作者の個性であるとも言えるだろう。
『南国飄飄』は、戦争を題材とした意欲的な作品だ。文章力もあるし、比喩のセンスもある。その点では、最終候補の中でいちばんの評価を得た。しかし、戦争体験者の老人を主人公に据えることの重みを、作者はどこまで背負う覚悟をしたのか。テーマではなく、手法の問題だと思う。個人的な意見だが、江見の視点から老人を描いた方が、より悲しみと再生を伝えられたのではないか。
『ホーム レス ホーム』は、物語の作りそのものはとてもシンプルだが、それが決してマイナスになっていない。主人公のアルバイトが「夜逃げの部屋の後片付け」という特殊な仕事だからだ。この辺りは読ませるし、読者の興味をそそる。私は「○」を付けた。ただ、やはり、着地点が想像通りに終わるのは物足りない。もうひとひねり欲しかった。
『熊猫の囁き』は、短篇向きではない、というのが最初の印象だった。もっと読みたいし、もっと書き込んで欲しい。主人公が中国人であるなら、日本で暮らすことの葛藤も描いて欲しい。それでも、物語全体を流れる、大らかさというか清々しさというか、それは他の作者にはない美点だった。書き続けることで、これからもどんどん筆力を上げてゆく方であろう。期待しています。おめでとうございます。
小説の気品
角田光代
「ホーム レス ホーム」は、じつに小説らしい作品だと思う。主人公のバイト先が内装業という設定もおもしろい。が、比喩を使いすぎて文章が安っぽくなってしまっているのが残念。それから主人公の父が産科医であることが不自然(背中のできものをなぜ産科医に診せるのか、の整合性)で、作者のご都合主義が目立ってしまう結果になり、それもまた残念である。
「南国飄飄」を、私はいちばんに推した。この作者は描写力に優れている。波照間島のむせ返るような自然とボルネオの荒々しい自然をなんでもなく書き分けてみせ、さらにたった一、二行で、江見や伊都子、敏子といった人物を立体的に描き出す。並大抵の筆力ではないと思う。しかしまったく惜しいことに、作者は、自身の筆力より物語の調和にばかり気を配っている。まず、義夫の過去と江見の過去を重ねることは甚だ不自然で無意味だし、ラストにピアスの青年まで登場させなくともいい。これほどの描写力がありながら、予定調和の物語を書くことなど、この作者にはまったく必要ない。自身に近い主人公を据え、ぜひもう一度、書いてほしい。私は本気でそれを読みたい。
「叙情的な癒し」は主人公、素子の、児童劇団に通っていた過去や、落語家の事務所の手伝いという設定はたいへんにおもしろいのに、それが生かし切れていない印象を持った。また読み進むうち、主人公だけが正しく、周囲はみんな馬鹿だったり空気が読めなかったりずるかったりするように思えてきて、少々苦しかった。母親も含め、周囲の人々の「そうしかできない」状況と、素子や真知子の「そうしかできない」日常をともに肯定的に書くことができれば、リアリティと読み応えと共感にあふれた小説になると思う。
「熊猫の囁き」は、じつに好感の持てる作品である。この好感の出どころは、ひとえに主人公、江遥の人の好さである。作者は、これほどのお人好しを書くのにまったく躊躇がなく、そのことが小説の気品になっていると思う。柳禾との学生時代のエピソードや、最初のアパートから見える景色、お好み焼屋「水月」の様子など、言葉で説明してはいないが何かおおらかな、ゆたかな光が、行間からさしこんでいる。「水月」のしのぶのひとり語りの陳腐さが気になるが、受賞作にふさわしい小説ではあると思う。
「愛の行為」のテーマにははっとさせられるところもあり、希のキャラクターには清潔な魅力があるのだが、いかんせん作者はそのテーマをありのままの言葉でくり返し説明しすぎである。くり返されればされるほど、生や死や愛というものの重みが減じてしまう。もっと読み手(選考委員という意味ではなく、書き手以外の人間)を信用して書いてみてもいいのではないかと思う。
この一作
小池昌代
「熊猫の囁き」が、群を抜いてよいと思った。出だしの一行目から、最初の一頁を読んで、わたしはもう、この作品に決めてしまった。文が運ばれていくときの「間」のようなものがいい。素直な流れがあって、押しつけがましくなく。
他の多くの候補作同様、だめ男が欲望のままにことをおこし、女が傷つけられるという状況が描かれるが、読後に清新な風が吹いてくるのは、主人公・江遥に、人間の、のどかな魅力があるせいである。
引き付けて考えれば、みな深刻な事態だろうが、それをふっと手放して眺めてみるという、一種、余裕の立ち位置があり、それがユーモアを呼びこんでいる。
江遥の夫の、遠縁の姪に当たる玉静がやってきて、ともに暮らすうち、夫と関係を結び、やがて孕んだ子を流産してしまう。世間ではありそうな、というより、いわゆる「小説」ネタとして描かれやすいようなできごとだが、玉静も、夫も、どこかかわいそうな弱き人々として描かれ、江遥本人にいたっては、流れた胎児を、自分の子供のように感じていたりする。この江遥、人がいいのか、いい人なのか。案外、悪人なのかもしれない。ともかく、これだけではまだわからない。彼女の大きさ、おおらかさは、中国文化が持つ「幅」なのかもしれない。わたしは江遥という女性を、もっと知りたくなった。
気になった点はある。二章の回想が長すぎないか。「クビにされた」という最後の行で、ようやく一章の場面と繋がった。
熊猫との会話シーンも、不自然でバランスが悪い。ましてやこれを題名に持ってくるべきではない。もし、こうしたあれこれを修正する情熱がわいてこなかったら、江遥の物語を、また新しく一行目から書き始めてみてほしい。大きな長い作品になるような気がする。それをわたしは読んでみたい。
才能あふれる新人
北上次郎
新人賞は新人作家を世に送りだすために存在するが、その新人賞が価値あるものになるかどうかは、そこから大きなスケールの新人作家がいかに誕生するかにかかっている。その意味で、昨年に引き続き、才能あふれる新人が生まれたことを喜びたい。
第二回の大賞受賞作、邢彦さんの「熊猫の囁き」は素晴らしい。ヒロインの江遥が淀屋橋の石の欄干に手を載せるとひんやりした感触が伝わってきて、川面に目をやると深い緑が見えるだけで他には何も見えないという冒頭と、同じ位置に立つラストの比較がさりげないぶんだけ余計に鮮やかだ。
ラストでは、その石の欄干が熱を持っていて、さらに川面に目をやると船が行き来している。橋の上にも人と車が往来して、地面の下には地下鉄が動いている。街が死んだように静まり返っている冒頭の淀屋橋と、生きている街を実感するラストの淀屋橋の落差に、このヒロインの成長が隠されている。それを声高に語らず、さりげなく描く節度が好ましい。
回想が長すぎて、つまりは構成に難があったり、お好み焼屋を営むしのぶという女性の過去語りが説明ぎりぎりであと一工夫欲しかったり、熊猫の意味が不明だったりと、細かなところを見ていけばけっして完璧な作品ではないが、それらは容易に直すことが出来るといっていい。むしろ、柳禾という友人の巧みな造形を始めとして、この作家の持つ美点に注目したい。この作品を読むと、私たちが忘れていること、たとえば前向きに生きることの大切さを、思い出させてくれる。それが図式に堕ちず、体の底のほうからこみ上げてくることこそ、そしてそういう力に満ちていることこそ、この作品の最大の美点だと思う。